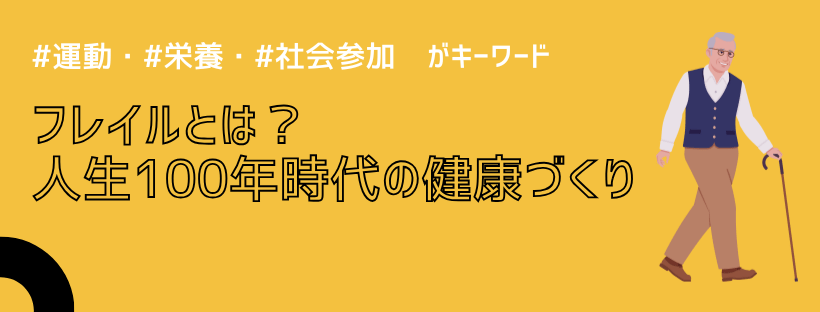質問文がここに表示されます。
第1章:フレイルとは?
― 健康と要介護の分かれ道 ―
「人生100年時代」と言われる今、私たちはこれまで以上に長いシニアライフを迎えます。
しかし、ただ長生きするだけでなく、「健康で自分らしく生きる」ためには、
避けては通れないキーワードがあります。それが「フレイル」です。
フレイルは「健康」と「要介護」の中間地点
フレイル(Frailty)とは日本語で「虚弱」を意味し、加齢に伴って心身の活力が低下し、
ささいなきっかけで要介護状態に陥りやすい状態を指します。
坂道をボールが転がる様子を想像してみてください。フレイルは坂の途中の踊り場のようなもの。
まだ踏ん張れば健康な状態に戻ることもできますが、何もしなければ坂の下まで転がり落ちてしまう、
非常に重要な時期なのです。
このフレイルには、互いに影響しあう3つの側面があります。
身体的フレイル
筋力低下、疲れやすさ、
活動量の低下など。
精神・心理的フレイル
気分の落ち込み、うつ、
認知機能の低下など。
社会的フレイル
孤立、閉じこもり、
社会とのつながりの希薄化など。
例えば、「足腰が弱り(身体的)」、外出が面倒になり(精神・心理的)、
友人との交流が減ってしまう(社会的)…というように、これらは悪循環を生みやすい特徴があります。