質問文がここに表示されます。
- ホーム
- ご注文例
- サービス一覧
- 導入実績
- コラム
- 健康経営関連
- 見えないコスト「プレゼンティーイズム」が会社を蝕む?データで見抜く生産性低下の本当のサイン
- 従業員の生産性低下、原因は5つの「隠れ不調」?データで始める具体的対策
- プロが解説!健康経営優良法人2026認定申請のポイントを5分で理解
- 健康経営優良法人2025|申請要件を簡単セルフチェック!中小企業・大規模法人別の必須項目を解説
- 明日から使える健康経営KPI 50選
- 健康経営の「現在地」を把握する。ベンチマーク診断で他社と比較し、次の一手を明確に
- 健康経営の「見えないコスト」を可視化する方法|シミュレーターで経済的損失を算出
- 健康経営は福利厚生から戦略投資の時代へ
- 【健康経営の新常識】プレゼンティーイズムとは?測定方法と4タイプ別改善策を専門家が徹底解説
- 【離職率改善】ワークエンゲージメントとは?測定ツールで組織の「熱意」を可視化する方法
- 若手が辞めない会社は「ウェルビーイング」を実践。Z世代の本音データから見る採用・定着の新常識
- アブセンティーズム(病欠)に潜むサインとは?「休み方」でわかる健康リスクと企業の対策
- 【担当者必見】ストレスチェック制度の「報告書作成」と「集団分析の活用法」を徹底解説
- 「健康経営」はなぜ儲かるのか? 生産性向上と企業価値を高める5つの理由
- 【データで見る】健康経営は儲かるのか?売上・生産性・採用への投資対効果を徹底解説
- 「健康投資のROI」を算出する3ステップ|経営層を“数字”で説得する実践ガイド
- 健康教育の新常識。「3分動画+テスト」が、従業員の“自分ごと化”と行動変容を促す理由
- 健康経営と人的資本|マイクロラーニングで生産性を高める戦略的eラーニング活用術
- 健康経営を成功に導く「社内ニーズ調査」の進め方【アンケート自動生成ツール付】
- 【2024年最新】健康経営ランキング市区町村別TOP20|データで見る採用・ブランディング戦略
- 【中小企業向け】健康経営はコストゼロから始められる!我が社流・成功の3ステップを解説
- 従業員の高齢化と健康支援
- 健康経営施策の年間計画
- 健康経営と効果
- 産業別健康動向調査
- メンタルヘルス関連
- 働き方・身体活動関連
- 食生活と栄養
- 女性の健康関連
- ヘルスリテラシー関連
- なぜ満足度91.8%?従業員の行動変योを促す健康セミナーの3つの理由
- 健康セミナーの効果測定|満足度だけで終わらせない
- 健康診断の結果を読み解くパーソナルレポート
- ヘルスリテラシーって何?
- ヘルスリテラシークイズ
- 企業と個人の喫煙によるコスト
- 国の新指針「睡眠ガイド2023」は企業へのメッセージ
- 健康寿命シミュレーター
- 健康診断の結果、見て見ぬフリはもう終わり。40代から知るべき男女別の健康リスク
- 『歯科健診』はコストか、投資か?データで示す「口腔」が企業リスクに直結する理由
- あなたの”何気ない生活習慣”が、会社の保険料を上げている?未来のコストを1分でシミュレーション
- 保存版|日本の健康統計データ。年代・性別で見る生活習慣の平均値まとめ【厚生労働省調査より】
- 健康行動デザイン
- なぜ社員は階段を使わないのか?行動デザインで「つい歩きたくなる」職場を作る3つの仕掛け
- ウォーキングイベント参加率を上げるには?「ソーシャル・ナッジ」で8割参加へ
- なぜ続かない?意志の力に頼らず「健康習慣」を自動化する“if-then”プラン術
- 特定保健指導の参加率を上げる「損失回避」とは?メリットを伝えるだけでは人は動かない
- 食堂の"メニュー名"と"配置"を変えるだけ。社員が自然とヘルシーな食事を選ぶ「食のナッジ」戦略
- 会議は“50分”が新常識。Googleも実践する「休む」を仕組み化し、燃え尽きを防ぐ時間デザイン術
- 「面倒くさい」を「すぐ予約」に変える。健診受診率95%超を目指す、行動科学に基づいた通知の“書き方”
- 健康セミナー人気テーマ一覧
- 無料ダウンロードコンテンツ
- 健康経営関連
- よくある質問/お客様の声
- 健康経営測定ツール集
- お問い合わせ
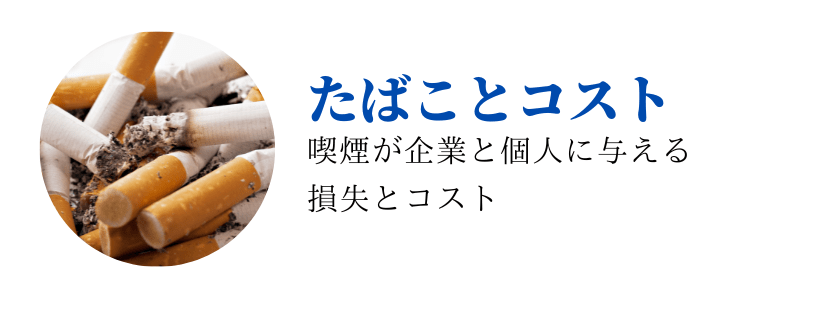
この記事のポイント
- 喫煙がもたらす社会全体の経済的損失が、年間約2兆円にものぼることがわかる
- 喫煙によるタバコ休憩や生産性低下(プレゼンティーズム)が、企業の大きな損失に繋がる理由が学べる
- タバコのニコチン依存が、なぜ違法薬物に匹敵するほど強力で、禁煙が難しいのかが理解できる
- 望まない受動喫煙による「スモハラ」が、企業の法的・経営的リスクになることがわかる
ご案内
社内報やオウンドメディアへの執筆・監修を承っております
たばこによる損失額は年間「2兆500億円」—健康と経済の両面から考える禁煙の重要性
社会全体で進む禁煙への取り組み
健康増進法の改正により、2019年7月から学校・病院・行政機関などでは敷地内禁煙が義務化され、2020年4月からは事務所・工場・飲食店なども原則屋内禁煙となり、初めて法制化されました。
これは本人の健康を守るだけでなく、望まない受動喫煙を防ぐための社会的な対策です。
日本たばこ産業(JT)の「2018年全国たばこ喫煙者率調査」によると、成人喫煙率は17.9%。タバコ税の増税により徐々に減少傾向にあるものの、加熱式タバコの普及もあり、依然として先進国の中では高い水準です。
世界では禁煙への取り組みがさらに進んでおり、2022年12月にはニュージーランドで「2009年1月1日以降に生まれた人は生涯紙たばこを購入できない」という法改正案が可決されるなど、国を挙げた対策が進行中です。
喫煙による健康被害と経済的損失
日本国内では、喫煙に関連する病気で亡くなる人は年間12〜13万人、世界では年間500万人以上と推定されています。
特に20歳以前に喫煙を始めた場合、男性は平均寿命が8年、女性は10年短くなるとされています。
2018年に厚生労働省が発表した研究によると、2015年度の喫煙による損失額は推計で2兆500億円。
がん治療費は5,000億円超、受動喫煙による医療費は3,300億円にのぼり、喫煙が社会全体に与える影響は極めて大きいことが分かります。
「健康のために禁煙を」だけでは届かない現実
喫煙者への禁煙推進講義では、「あなたの健康を害しています」と伝えても、「そんなことは耳にタコができるほど聞いている」と一蹴されることも少なくありません。
喫煙による健康被害はすぐに現れるものではなく、生活習慣病など徐々に進行するため、現実味が薄く、禁煙の必要性は理解していても行動に移す人は限られています。
だからこそ、今回は「健康」だけでなく「経済的な損失」という視点から、喫煙の影響を見つめ直すことが重要です。
従業員の健康維持だけでなく、企業の生産性や社会的責任を果たすためにも、禁煙は今後の大きな課題です。
POINT
喫煙は健康だけでなく、社会・企業・個人の経済にも大きな損失をもたらします。
禁煙は「個人の選択」ではなく、「社会全体の責任」として捉えるべき時代です。
今後の企業活動においても、従業員の健康支援と禁煙推進は、持続可能な経営の柱となるでしょう。
違法薬物に匹敵するたばこの依存性と企業の生産性への影響
禁煙は生産性向上につながる
経済産業研究所の報告によると、禁煙は企業の生産性向上に寄与することが明らかになっています。
その理由の一つが、アブセンティーイズム(欠勤・休職)や、プレゼンティーイズム(出勤しているがパフォーマンスが低下している状態)の改善です。
喫煙や受動喫煙は、身体的・精神的な倦怠感を引き起こし、集中力の低下や業務効率の悪化を招きます。禁煙によってこれらの不調が改善されることで、従業員のパフォーマンスが向上し、企業全体の生産性が高まるのです。
ニコチンは違法薬物に匹敵する依存性を持つ
タバコに含まれるニコチンは、非常に強い依存性を持つ物質です。
使用者が依存症になる割合は、ニコチン > ヘロイン > コカイン > アルコール > カフェインとされており、ニコチンは合法でありながら、違法薬物に匹敵する依存性を持っています。
また、禁断症状の強さも、アルコール > ヘロイン > ニコチン > コカイン > カフェインの順であり、ニコチン依存症からの脱却は非常に困難であることが分かります。
出典:Royal College of Physicians「Nicotine Addiction in Britain」(2000年)
POINT
ニコチンは合法でありながら、依存性・禁断症状ともに違法薬物と同等レベルの危険性を持っています。
喫煙による健康被害だけでなく、企業の生産性や職場環境にも悪影響を及ぼすため、禁煙は個人の選択ではなく、企業全体で取り組むべき健康経営の課題です。
喫煙と企業の生産性損失の関係
喫煙者は非喫煙者よりも生産性の損失が大きい
米国の民間企業を対象とした調査によると、喫煙者による年間損失は以下の通りです:
・アブセンティーイズム(欠勤): 517ドル
・プレゼンティーイズム(出勤しているが生産性が低い): 462ドル
・タバコ休憩による損失: 3,077ドル
特にタバコ休憩による損失は、他の要因の6倍以上にも上ると報告されています(Berman et al., 2014)。
日本での禁煙プログラムの成果
日本で実施された禁煙プログラムでは、参加者73名中、禁煙支援対象者44名のうち33名が禁煙に成功しました。
・タバコ休憩時間:1日あたり約27分減少
・禁煙成功者のみ:約50分減少
・プレゼンティーイズム:0.5標準偏差改善
・ストレス:0.9標準偏差軽減
・病欠日数:0.5日減少
・健康問題による早退日数:0.4日減少
これらの結果から、禁煙は企業の生産性向上に大きく貢献することが示されています。
出典・参考資料
詳細な研究内容は、以下のリンクからご覧いただけます:
https://www
喫煙は人間関係や企業リスクに影響する⁉
喫煙が職場の印象や信頼感に与える影響
喫煙は稼働時間だけでなく、職場での人間関係にも支障をきたすという調査結果があります。
仕事の相手が喫煙者だった場合、36.8%の人が好感度が低下したと回答。
また、仕事へのモチベーションやコミュニケーション意欲も約30%低下する傾向が見られました。
信頼感の低下(26.4%)や、購買意欲の低下(55.9%)といった影響も報告されており、営業職では成績に直結する可能性があります。
不快感の主な理由はタバコの匂いや煙であり、休憩時間の不公平感も次点として挙げられています。
スモークハラスメント(スモハラ)の実態と裁判事例
近年、“スモハラ”と呼ばれる受動喫煙によるトラブルが急増しています。
実際の裁判事例では、
・自動車教習所運営会社が100万円の和解金を支払い
・大手企業が350万円の和解金を支払うなどのケースが報道されています。
企業が受動喫煙対策を怠ることで、法的・経営的リスクを抱える可能性があることが示されています。
労働安全衛生法と企業の責任
労働安全衛生法第68条の2では、事業者は労働者の受動喫煙を防止するため、実情に応じて適切な措置を講ずるよう努めると明記されています。
この努力義務は企業規模を問わずすべての事業者に適用され、厚生労働省のガイドラインに基づいて、経営者や幹部が率先して禁煙推進に取り組む必要があります。
特にマネジメント層が喫煙者である場合、禁煙施策が進みにくい傾向があるため、意識改革が求められます。
スモハラ対策として企業が押さえるべきポイント
- 妊婦や持病のある従業員の有無など、自社の現状を把握する
- 屋内全面禁煙や適切な分煙を徹底し、空気環境の基準を確認する
- 管理職・従業員に対して受動喫煙や禁煙に関する教育・啓発を行う
経営面や社内トラブルの予防のためにも、禁煙推進は企業にとって重要な取り組みです。
値上がりを続ける喫煙によるコスト
生涯でかかるタバコ代は1,000万円超⁉
20歳から70歳まで、1日20本のタバコを吸い続けた場合、1箱600円換算で約1,100万円のタバコ代がかかると試算されています。
これはあくまで本体価格のみであり、ライター・灰皿・医療費などを含めるとさらに多額の支出が予想されます。
タバコ価格は今後も上昇傾向
1998年に創設されたたばこ特別税の当時、タバコの平均価格は約200円でしたが、2020年には約2.5倍の価格にまで上昇しています。
欧米諸国では1箱1,000円を超える国も存在しており、日本の価格はまだ安い部類に入りますが、今後も増税の対象としてたばこ税が筆頭に挙げられる可能性が高く、家計への負担はさらに重くなると予想されます。
経済的観点からも禁煙は重要な課題
喫煙による健康被害だけでなく、企業・個人の経済的負担を考慮すると、禁煙は今後の大きな課題と言えます。
現在では禁煙外来の保険適用基準も緩和されており、企業としても従業員の健康とコスト削減のために、会社全体で禁煙に向けた取り組みを進めることが求められています。
喫煙の損失とコストに関する総括
喫煙は健康被害だけでなく、個人の経済的負担、職場での人間関係、企業の生産性、そして社会的コストにまで影響を及ぼします。
特に近年では、たばこ税の増加や医療費の上昇により、喫煙による金銭的損失はますます深刻化しています。
禁煙は、健康を守るだけでなく、経済的・社会的な損失を防ぐための重要な選択肢であり、個人だけでなく企業や社会全体で取り組むべき課題です。