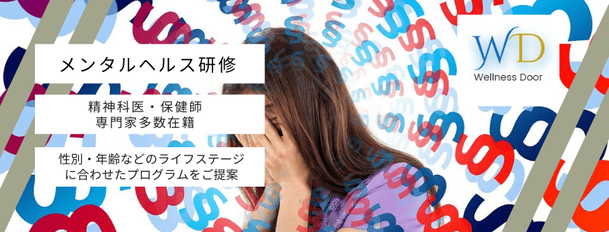質問文がここに表示されます。
- ホーム
- ご注文例
- サービス一覧
- 導入実績
- コラム
- 健康経営関連
- 見えないコスト「プレゼンティーイズム」が会社を蝕む?データで見抜く生産性低下の本当のサイン
- 従業員の生産性低下、原因は5つの「隠れ不調」?データで始める具体的対策
- プロが解説!健康経営優良法人2026認定申請のポイントを5分で理解
- 健康経営優良法人2025|申請要件を簡単セルフチェック!中小企業・大規模法人別の必須項目を解説
- 明日から使える健康経営KPI 50選
- 健康経営の「現在地」を把握する。ベンチマーク診断で他社と比較し、次の一手を明確に
- 健康経営の「見えないコスト」を可視化する方法|シミュレーターで経済的損失を算出
- 健康経営は福利厚生から戦略投資の時代へ
- 【健康経営の新常識】プレゼンティーイズムとは?測定方法と4タイプ別改善策を専門家が徹底解説
- 【離職率改善】ワークエンゲージメントとは?測定ツールで組織の「熱意」を可視化する方法
- 若手が辞めない会社は「ウェルビーイング」を実践。Z世代の本音データから見る採用・定着の新常識
- アブセンティーズム(病欠)に潜むサインとは?「休み方」でわかる健康リスクと企業の対策
- 【担当者必見】ストレスチェック制度の「報告書作成」と「集団分析の活用法」を徹底解説
- 「健康経営」はなぜ儲かるのか? 生産性向上と企業価値を高める5つの理由
- 【データで見る】健康経営は儲かるのか?売上・生産性・採用への投資対効果を徹底解説
- 「健康投資のROI」を算出する3ステップ|経営層を“数字”で説得する実践ガイド
- 健康教育の新常識。「3分動画+テスト」が、従業員の“自分ごと化”と行動変容を促す理由
- 健康経営と人的資本|マイクロラーニングで生産性を高める戦略的eラーニング活用術
- 健康経営を成功に導く「社内ニーズ調査」の進め方【アンケート自動生成ツール付】
- 【2024年最新】健康経営ランキング市区町村別TOP20|データで見る採用・ブランディング戦略
- 【中小企業向け】健康経営はコストゼロから始められる!我が社流・成功の3ステップを解説
- 健康経営の次の一手。「治療と仕事の両立支援」を始める3つのステップ
- 『育休取得』で終わらせない。男女ともにキャリアを止めない「育業」時代の両立支援
- 経営リスク「介護離職」は突然やってくる。40代・50代の“沈黙の退職”を防ぐ組織の作り方
- 部下の「病気」と向き合う。治療と仕事を両立させる個別支援の進め方
- 従業員の高齢化と健康支援
- 健康経営施策の年間計画
- 健康経営と効果
- 産業別健康動向調査
- メンタルヘルス関連
- 働き方・身体活動関連
- 食生活と栄養
- 女性の健康関連
- ヘルスリテラシー関連
- なぜ満足度91.8%?従業員の行動変化を促す健康セミナーの3つの理由
- 健康セミナーの効果測定|満足度だけで終わらせない
- 健康診断の結果を読み解くパーソナルレポート
- ヘルスリテラシーって何?
- ヘルスリテラシークイズ
- 企業と個人の喫煙によるコスト
- 国の新指針「睡眠ガイド2023」は企業へのメッセージ
- 健康寿命シミュレーター
- 健康診断の結果、見て見ぬフリはもう終わり。40代から知るべき男女別の健康リスク
- 『歯科健診』はコストか、投資か?データで示す「口腔」が企業リスクに直結する理由
- あなたの”何気ない生活習慣”が、会社の保険料を上げている?未来のコストを1分でシミュレーション
- 保存版|日本の健康統計データ。年代・性別で見る生活習慣の平均値まとめ【厚生労働省調査より】
- 健康行動デザイン
- なぜ社員は階段を使わないのか?行動デザインで「つい歩きたくなる」職場を作る3つの仕掛け
- ウォーキングイベント参加率を上げるには?「ソーシャル・ナッジ」で8割参加へ
- なぜ続かない?意志の力に頼らず「健康習慣」を自動化する“if-then”プラン術
- 特定保健指導の参加率を上げる「損失回避」とは?メリットを伝えるだけでは人は動かない
- 食堂の"メニュー名"と"配置"を変えるだけ。社員が自然とヘルシーな食事を選ぶ「食のナッジ」戦略
- 会議は“50分”が新常識。Googleも実践する「休む」を仕組み化し、燃え尽きを防ぐ時間デザイン術
- 「面倒くさい」を「すぐ予約」に変える。健診受診率95%超を目指す、行動科学に基づいた通知の“書き方”
- 健康セミナー人気テーマ一覧
- 無料ダウンロードコンテンツ
- 健康経営関連
- よくある質問/お客様の声
- 健康経営測定ツール集
- お問い合わせ

この記事のポイント
- リモートワークがもたらす「生活リズムの乱れ」と「コミュニケーションの減少」という2大メンタルヘルスリスクがわかる
- 雑談や相談の機会が減ることで、なぜ孤独感や孤立感が強まり、ストレスに繋がるのかが学べる
- 生活リズムを整え、心身の健康を保つための具体的なセルフケア方法が手に入る
- 個人だけでなく、チームや企業として心理的安全性を高め、孤立を防ぐ仕組みづくりの重要性が理解できる
リモートワークのメンタルヘルス
在宅勤務(テレワーク・リモートワーク)におけるメンタルヘルスについて、精神科医・産業医がそのリスクと課題、セルフケアについて解説します。
目次
- (1)リモートワークにおけるメンタルヘルスとリスク
- (2)コミュニケーションの減少が与えるストレス
- (3)セルフケア
(1)リモートワークにおけるメンタルヘルスとリスク
リモートワークでは、通勤や対面のやり取りが減ることで、生活リズムの乱れや孤立感が生じやすくなります。
精神的な不調や生産性の低下につながるリスクがあるため、企業側の配慮と個人の意識が重要です。
(2)コミュニケーションの減少が与えるストレス
オンライン中心の業務では、雑談や相談の機会が減少し、孤独感・孤立感が強まる傾向があります。
漠然とした不安感やストレスを感じる人も多く、チーム内での定期的な交流やフィードバックが求められます。
(3)セルフケア
リモート環境でも心身の健康を保つためには、生活リズムの維持・運動・休憩・相談の場づくりが大切です。
自分の状態を客観的に把握し、必要に応じて専門家の支援を受けることも有効です。
リモートワークの普及に伴い、メンタルヘルスへの配慮はますます重要になっています。
孤独感や不安感への対応は、個人だけでなく企業全体で取り組むべき課題です。
ご案内
社内報やオウンドメディアへの執筆・監修を承っております
(1)リモートワークにおけるメンタルヘルスとリスク
生活リズムが変化するリモートワーク
コロナウイルスの世界的流行により、リモートワークが急速に普及しました。
実は厚生労働省は2017年からICT活用を推奨しており、働き方改革の一環としてテレワークはすでに準備されていた制度です。
フレキシブルな働き方は、子育て世代や地方在住者の労働機会を広げ、通勤時間の削減によって生活の質向上にもつながります。
しかし、急な変化に戸惑い、適応できずに悩む人も少なくありません。
リモートワークがメンタルに与える影響①:生活リズムの乱れ
通勤がなくなり、起床・就寝時間が不規則になることで、on-offの切り替えが困難になります。
集中力が低下し、タスクに時間がかかるようになり、結果的に残業が増加。
運動不足やストレスも加わり、睡眠の質が悪化することで、生活習慣の乱れがメンタル不調に直結します。
ポイント:朝のルーティンを整えることが、心身の安定につながります。
リモートワークがメンタルに与える影響②:コミュニケーションの減少
社内の雑談や相談の機会が減り、孤独感・孤立感を感じる人が増えています。
精神科外来でも、リモートワークによる人間関係の希薄化が原因と思われる相談が増加。
会社内だけでなく、友人との交流も減ることで、漠然とした不安感が心を蝕むケースもあります。
ポイント:定期的なオンライン面談や雑談の場を設けることで、心理的安全性を高めることができます。
(2)コミュニケーションの減少が与えるストレス
社内のやり取りが減ることで生じるストレス
リモートワークでは、社員同士の雑談や相談の機会が減少し、心理的な距離感が生まれやすくなります。
チャットツールの導入などで対策は進んでいますが、対面で得られる表情・声のトーン・空気感などが失われ、誤解や不快感につながることもあります。
特にITに不慣れな世代では、オンラインでのやり取りに強いストレスを感じる傾向があります。
ポイント:チャットだけでなく、定期的なビデオ通話や1on1ミーティングを活用し、関係性の維持を図ることが重要です。
新入社員と上司の間に生じる壁
リモート環境では、相手の状況が見えないため、質問や相談のタイミングが掴みにくくなります。
新入社員は「今聞いてもいいのか?」という不安を抱え、上司も部下の状態を把握しづらく、指導が難しくなるという声が多く聞かれます。
オンラインでは文面のみのやり取りとなり、非言語情報が欠落
心理的安全性:安心して意見や相談ができる関係性を築くためには、上司側の積極的な声かけや、相談しやすい雰囲気づくりが不可欠です。
孤独感・孤立感がもたらすメンタルへの影響
外出制限により、仕事もプライベートも家の中で完結する生活が続くと、人と接する機会が激減します。
一人暮らしの方では、1日の会話量がほぼゼロになるケースもあり、漠然とした不安感が心を蝕む原因となります。
気づかないうちに涙が出る、朝起きられないなどの症状が現れ、限界まで我慢してしまう人も少なくありません。
関連情報:人間は1日平均15,000語を話すと言われており、会話量の減少はメンタル不調のリスクを高めます(2007年 米国科学誌「Science」より)。
ポイント:孤立を防ぐためには、オンラインでも「誰かとつながっている」感覚を持てる仕組みが必要です。
(3)セルフケアと環境づくり
生活習慣を整えることがセルフケアの第一歩
外出や友人との交流が制限される中、自分自身をケアする力が求められています。
特に重要なのは、仕事とプライベートのon-offを明確にすること。
通勤がなくなったことで、ギリギリまで寝て部屋着のまま作業する人も増えていますが、これは心身の切り替えを妨げる要因になります。
ポイント:起床時間を一定に保ち、朝のストレッチやラジオ体操などで脳と体を目覚めさせましょう。
関連情報:ドイツの調査では、体内リズムの変化に慣れるまで平均3週間かかるとされ、夜型の人は4週間経っても改善しない傾向があると報告されています(日本睡眠学会)。
作業環境が心身に与える影響
ベッドやソファでの作業は、姿勢が悪くなり、背骨や神経への負担が増加します。
自律神経が乱れることで、睡眠・消化・血圧などに影響が出る可能性も。
また、デスク周りが散らかっていると、視覚的なストレスが集中力を低下させます。
ポイント:「デスクの散らかりは心の散らかり」。作業スペースを整えることで、心も整います。
家庭との距離感とセルフケア
家族と過ごす時間が増える一方で、仕事と家庭の境界が曖昧になり、ストレスを感じる人もいます。
配偶者や子どもとの距離感に悩むケースは、夫婦カウンセリングでも増加傾向にあります。
家族もリモート環境に慣れていないため、お互いに理解し合う時間と対話が必要です。
ポイント:家庭内でも「仕事時間」と「家族時間」を明確に分けることで、ストレスを軽減できます。
総括:リモートワーク時代の心のケアとは
リモートワークは、柔軟な働き方を可能にする一方で、生活リズムの乱れやコミュニケーション不足によるメンタルヘルスへの影響が懸念されています。
その中で私たちができることは、自分自身の生活習慣を整え、働く環境を見直し、周囲とのつながりを意識的に保つことです。
企業やチームとしても、心理的安全性を高める取り組みや、孤立を防ぐ仕組みづくりが求められています。
心の不調は目に見えにくく、気づいたときには深刻化していることもあります。だからこそ、日々のセルフケアと小さな違和感への気づきが、健やかな働き方への第一歩となります。
リモートワークが当たり前になった今、心と体のバランスを保つことは、働くすべての人にとっての共通課題です。
ひとりで抱え込まず、必要なときには専門家の力を借りることも、立派なセルフケアのひとつです。
リモートワークのメンタルヘルス 理解度クイズ
お問い合わせ
メンタルヘルスをテーマとした健康セミナー・研修のお問い合わせはこちら